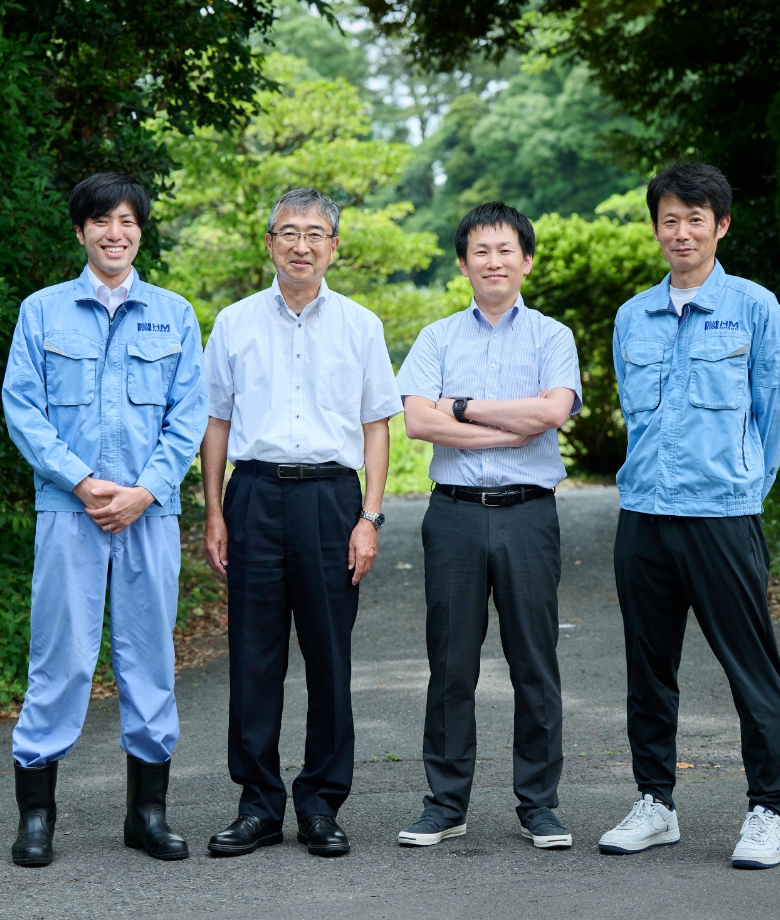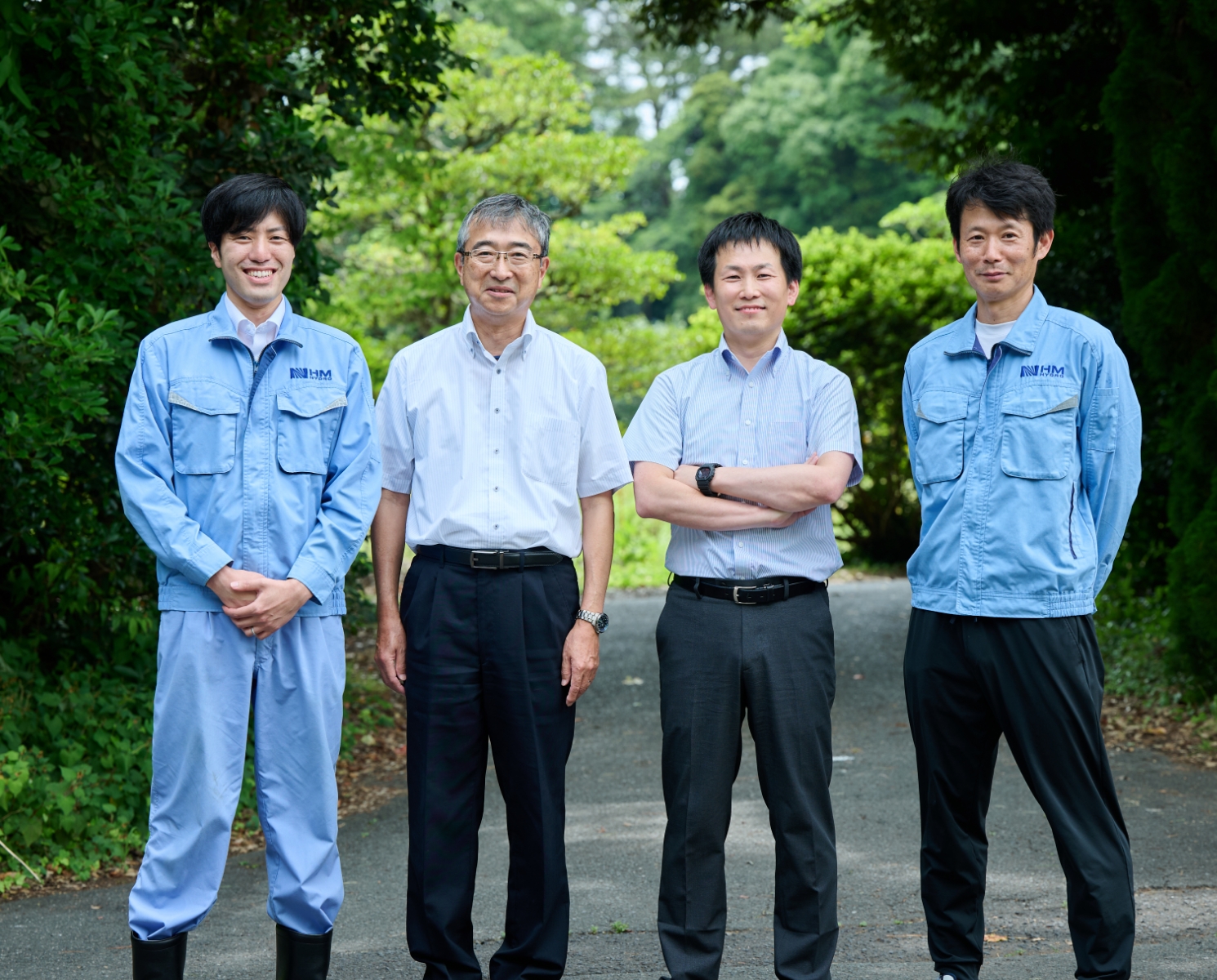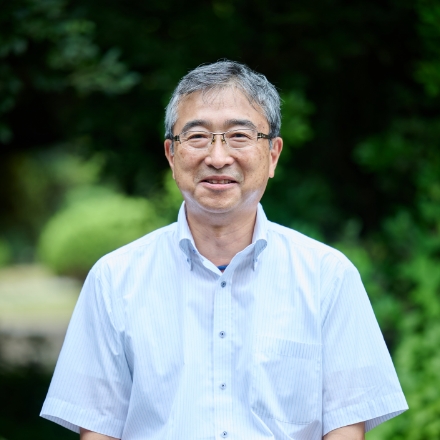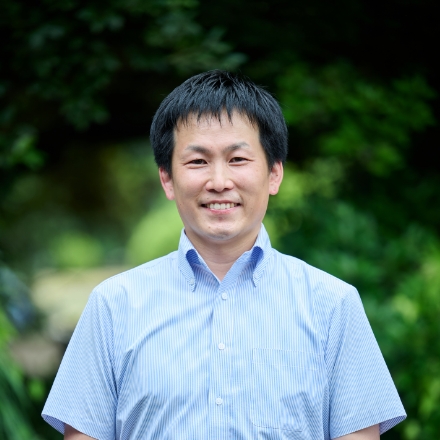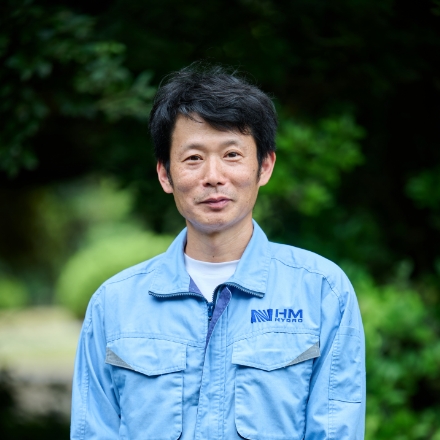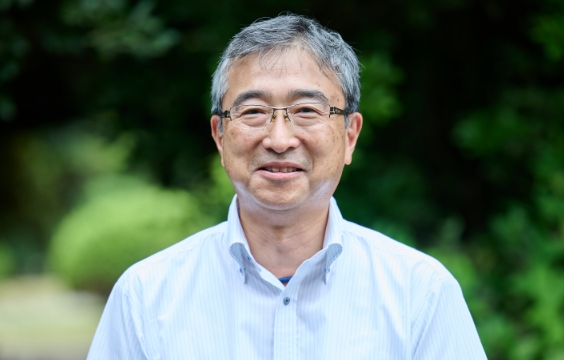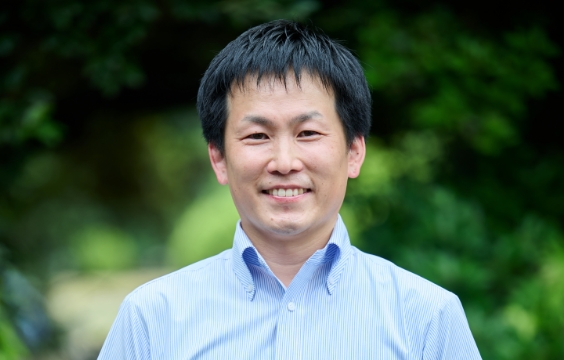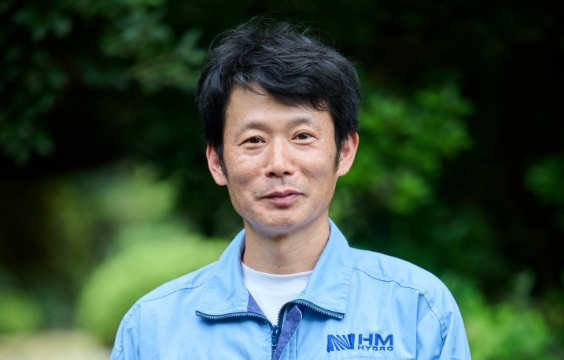Story 1
塚原発電所プロジェクトの始動
他社製の更新案件に挑む
プロジェクトが動き出したのは2006年。日立製作所九州支社の営業チームは、九州電力が、塚原発電所の総合更新を計画しているという情報を入手していた。2011年10月の日立三菱水力の設立後に行われた入札は、同発電所の既設水車発電機が他社製ということもあり、激しい価格競争となった。しかし、日立三菱水力は、九州最大の水力発電所である小丸川発電所(最大出力120万kW)を手がけた実績と優れた技術提案を買われ、第一交渉権を得ることができた。
受注すれば、総額20億円を超えるビッグプロジェクト。計画では、既設4台(1台あたり最大出力15,650kW)の水車発電機を、2台(1台あたり最大出力33,300kW)に集約、加えて、台風による浸水被害を受けた発電所の建屋を、浸水リスクの低い隣接地点に移設するという新設発電所建設と同等の計画だった。
このプロジェクトを、顧客側との技術窓口として、提案活動から運転開始まで一貫してリードしたのが、日立製作所(現日立三菱水力)の「水力技術部」だ。水力技術部は、設計、製造、品質保証といった社内の技術部門を取りまとめ、品質、工程、コストを管理する、いわばオーケストラの指揮者のような存在。水力技術部の指揮のもとで、各部門の技術者たちが動き出した。
前例のない新技術を提案
水車発電機の更新において、ポイントになったのは大きく2つ。1台あたりの発電量をいかにアップさせるか。そして、いかに機器のメンテナンスを容易にするか。昭和初期の技術で作られた古い水車発電機は、油圧による操作や河川水を利用した水冷方式などの設備メンテナンスに手間がかかるため、保守・運用面での課題になっていた。
日立製作所は、高性能化に加え、河川水を使用しない冷却方式等保守の簡素化につながるさまざまな新技術を提案した。中でも、水車に流入する水量を調節するための羽根(水車ガイドベーン)を、従来の油圧ではなく2機の電動装置で操作する「複動式電動サーボ」は、前例のないものだった。
こうした提案活動を続けていた最中に、日立製作所、三菱電機、三菱重工業の3社が水力事業を統合、2011年10月に「日立三菱水力」が発足した。そして、その翌年の2012年に本プロジェクトの入札が行われ、6年越しの提案活動の末に日立三菱水力が見事に受注の内示を獲得。設立間もない日立三菱水力にとって、塚原発電所の更新工事の受注は、社内に大きな希望と勇気を与えるものになった。

複動式電動サーボ
Story 2
若き設計者の挑戦
図面に込めた想い
水車発電機の要となる水車の設計を担当したのは、入社8年目のYだった。一口に「水車」と言っても、その構成部品は数も多く、水の位置エネルギーを運動エネルギーに変換する「ランナ」、水車に水が流れ込む流路となる「ケーシング」から、水を排出する「下部吸い出し管(ドラフトチューブ)」、流れ込む水量を調整する機構まで多岐にわたる。Yは設計の主担当として、それら水車部品の構造設計、生産設計を担った。
Yには期する想いがあった。それまで彼は、水車の予防保全工事の設計しか経験がなく、水車の新設や更新といった大規模案件を担当するのは今回が初めてだった。「ようやく、やれる」。地道に仕事を積み重ねてきて、やっと巡ってきたチャンスだった。「我々が作る製品は、とても寿命が長いものです。納入して終わりではなく、その先も不具合なく動き続ける物を作るという意味も含めて、この仕事をやり遂げようと決意しました」。


ボルト1本からの新設計
しかし、Yの想いを試すように、設計作業は困難の連続だった。既設の水車は他社製であり、かつ仕様も異なるため、日立三菱水力による新たな設計として取り組んだ。発電所の特性に合わせた一品一様の設計とものづくりにおいて、市販で調達できるような部品はほとんどなく、ボルト1本から形状や素材などの仕様を検討し、図面化しなければならない。Yがこれまで担ってきた予防保全の設計に比べて、検討すべき項目がはるかに多く、その内容も大きく違っていた。また、部品点数の多さに比例して設計書や図面枚数も増え、Yは、資料や図面の作成、関係部門の取りまとめに追われた。
もちろん、黙々と図面に向かうだけが設計者の仕事ではない。Yは、過去の日立や三菱の図面を調べ、ベテランの技術者に教えを請うた。上司や部下を巻き込み、関係部門との協力関係を構築しながら、一つひとつ課題を乗り越えていった。

下部吸い出し管(ドラフトチューブ)の据え付け
Story 3
発電所の心臓部を組み立てる


入念な工事計画と、現場環境の構築
設計作業と並行して、塚原の現地では2014年に土木工事が開始され、水力発電プラントの建設に向けた準備が進められていた。プラント工事の計画を担当したのは、プラント建設部の専任技師、H。工事に先立つ見積段階からプロジェクトに加わり、施工安全計画書の作成などを進めていた。
プラント工事は地元の建設工事会社と分担することになり、日立三菱水力は、水車埋設品(吸い出し管、ケーシング)の現地溶接作業、発電機の固定子・回転子の現地組み立てといった特殊作業を請け負うことになった。多くの施工業者や職人が出入りする現場で、Hは仮設事務所の場所を確保すべく、現地での環境構築に奔走した。それと同時に、現地での製品組み立てに伴う搬入経路の計画も、Hの仕事だった。部品を載せたトレーラーが設置場所まで近づけない場合は、専用のクレーンを手配して部品を一度仮置きし、そこからコロ引きをして設置場所に搬入するなど、現場の立地条件に合わせた地道な対応を積み重ねていった。
工事直前の思わぬ行き違い
2018年、いよいよ発電所の心臓部とも言える発電機の固定子・回転子の組み立て工事が始まろうとしていた。しかしその矢先、現地作業所掌区分について、九州電力側と認識の行き違いが判明。実際の組み立てを行う「作業員」と、組み立て作業をサポートする「助勢員」の担当区分が曖昧になっていたことが原因だった。Hは改めて両社の責任範囲を整理・明確化し、所掌区分表を作成。無事に工事が開始され、およそ1年がかりで、発電機2台分の固定子・回転子の組み立て工事が完了した。

回転子の吊り込み
Story 4
チームでピンチを乗り越える
予期せぬ不具合の発生
困難を伴うプロジェクトゆえに、思わぬ壁にぶつかることも少なくなかった。現地での工事も終盤に差し掛かろうとしていた2019年、ある部品に予期せぬ不具合が見つかった。わずか数ミリの誤差によって、工事は一時中断。部品の再製作を余儀なくされた。
工期全体への影響が懸念される中、プロジェクトの「指揮者」として事態の収束に奔走したのが水力技術部のSだった。前任者からプロジェクトマネージャーの任を引き継いだばかりだった。Sはまず営業とともに客先に出向き、不具合を謝罪。次に社内の各部門と連携し対処法および再発防止策の取りまとめを行った。また、据付フローの見直し(工事が中断しないように、作業順序の入れ替え)を提案し、九州電力および工事を請け負っている地場の業者に掛け合った。


モノではなく、人に向き合う
ものづくりの仕事は、決して1つの部署で完結するものではない。さまざまな部署が連携して動く中で、どこかが躓けば、工期全体が遅れる方向に向かう。それを避けるために、Sはプロジェクト全体に目を配り、遅れそうな箇所があれば声をかける。そして、万が一何か起きた時は、「それを1部署で終わらせず、各部署で連携してチームで対処することが大切」だと語る。
「すべてが上手くいくなら、私は必要ありませんから」。そう笑いながら、Sは言う。「私は、プロジェクトマネージャーとしてものづくりの進行管理をしていますが、自分で設計ができるわけでもなく、人に動いてもらうしかない立場です。だからこそ、モノではなく、お客様も含めて『人』に向き合うことが私の仕事だと思っています」。Sの真摯な対応によって関係各所がすばやく連携し、工期の遅延を最小限に食い止めた。
Story 5
プロジェクト最後の砦


未知なるシミュレーションとの戦い
固定子・回転子の組み立て工事が終わると、順次、現地での製品試験が行われる。試験を担当する品質保証部は、製品の性能や品質をチェックする、いわばものづくりの番人だ。現地で試験を行うだけでなく、設計の初期段階からプロジェクトに参画し、図面のレビューや試験要領書の作成、工場での試験を行いながら、製品開発に伴走してきた。
品質保証部で入社5年目のTは、製品開発試験の終盤からプロジェクトに加わり、工場での試験や現地での試運転を担当することになった。試験と言っても、単に図面通りの仕様をチェックするだけではない。検査項目は多岐にわたり、中でもTを悩ませたのは、さまざまな不具合を想定して行われる「保護思想」の検証だった。例えば、電動サーボを動かす制御盤の部品が故障した場合、どのようにして水車発電機を安全に停止できるか。あるいは、電動サーボが機械的に故障した場合は、どのようにして水車発電機を安全に停止できるかなど、さまざまな不具合パターンを想定しながら、あらかじめ設計された保護思想の通りに装置が作動するのか、何通りものシミュレーションが行われた。特に「複動式電動サーボ」などの新設計品の試験では、未知なる不具合に対する保護思想を検証しなければならず、前例のない中でのシミュレーションにTは苦心した。
試運転は、緊張の連続
製品試験を終えると、プロジェクトはいよいよ佳境を迎え、2019年11月、現地での試運転が始まった。まずは、水を入れない状態での無水試験が行われ、各機器の単体試験、機器間のインターフェースをチェックしていく。試験は現地で初めて組みあがったものを実際に動かすので慎重にチェックをしていく必要があり、九州電力の担当者らも見守る中で、緊張感のある試験が続いていく。単体での試験が終わると、次はすべての機器を組み合わせた状態で無水での総合的な試験、そして、それが終わるといよいよ有水での試運転(有水試験)へと移っていく。
有水試験の最初は「初回転」と呼ばれ、固定部と回転部の接触がないか、異音や異臭がしないか、五感を研ぎ澄ませながらチェックを行う。この「初回転」に合わせて「初回転式」が執り行われ、新しい発電所の記念すべき初回転を、多くの関係者が見守った。運転開始に向けてさまざまな試験が続く中、2020年の年が明けると、世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大。プロジェクトにも暗雲が立ち込めるかに思えたが、Tたちは厳重な感染対策をしながら試運転を続け、数々の技術的な困難を乗り越え、無事にすべての試験をやり切った。
九州電力は2020年4月15日に「塚原発電所1号機の営業運転開始」、2020年5月28日に「塚原発電所2号機の営業運転開始」を知らせるプレスリリースを配信。ここに、およそ14年におよぶプロジェクトが実を結び、年間発電量約24,360万kWh、一般家庭約81,000世帯分を賄う新しい発電所が誕生した。

発電所全景